生徒・教員ブログ
神戸学習館
2023.11.01
「強さ」とは
10/8、ラグビーW杯で日本(世界ランキング12位)は、アルゼンチン(同9位)に27-39のスコアで負け、残念ながら2大会連続の決勝トーナメント進出を果たせませんでした。
私はラグビーのルールを全て理解しているわけではありませんが、それでもTVを食い入るように観てしまい、知らぬ間に自分の体にも力が入り声を上げていました。
前大会でその凄さに衝撃を受け、心を動かされた経験がまさによみがえった瞬間でした。
試合終了後、海外メディアや大会の公式X(旧Twitter)などでも、日本代表選手の行動や試合の称賛が取り上げられました。
これほどまでに大きな感動を与えてくれたのであれば、勝った負けたなど関係ないと思うのですが、選手たちは本当に悔しかったに違いありません。
勝敗が決まるプロスポーツの世界は皆が頂上を目指します。
強いチームに勝たなければ頂点には辿り着けません。
いわゆる強豪チームにおいては、環境整備に資金や人材が投入され、メンタル面やフィジカル面の差はほとんどないように感じます。
差が出てくるのは、選手やスタッフ、関係者の方々の“人間力”だと思います。
今回のW杯を観て、『強さ』とは、「何としても応援したいという周囲の人間の気持ちを高め、人の心を動かしていく力」だと思いました。
皆さんにとっての『強さ』とは何でしょうか?
こういった機会に自分なりに少し考えてみる、そんな時間も大切かもしれません。
Q.不登校にならないためには?
不登校になってしまったら、なってしまった理由は自分が一番よくわかっているはずです。
もしすぐに助けが必要な状況であれば、まずは助けを求めなければなりません。
そうではない場合は、まずは「登校しなければ・・」と焦ってジタバタしないことです。
やらなければいけないこと、やりたいことを、その時は周りに協力してもらいながら、自分のペースでやっていけば良いのです。
それは誰に咎められることでもありません。
大切なのは完全に不登校になってしまうまでの行動です。
どうしても一人で悩んでしまい、負のスパイラルに陥ります。
一番しんどい時期ですが、この時に最大の勇気と力を振り絞ってSOSを発信することです。
両親、兄妹、親族、先生、友だち、近所の人など、誰かにSOSが届くようにがんばるのです。
それでも不登校になってしまうこともあるでしょう。
しかし、不登校で人生が閉ざされるわけではありません。
人生100年時代、その気になれば転機はいくらでも訪れます。
不登校にはならない方が良いが、なったとしても何とかなるという開き直りが、次の転機に繋がるかもしれません。
2023.08.25
心躍る祭り~よさこい~
夏といえば皆さん何を思い浮かべますか?
地元が高知県の私は必ず「よさこい」が思い浮かびます。
毎年8月9日~12日にかけて催されますが、今回は4年ぶりの開催。
そして第70回目になります!
よさこいの起源は諸説あり、特定されていないそうですが、高知のよさこい祭りにはルールがあります。
①鳴子を手に持ち前進する踊りの振付けが基本。
②曲のアレンジ可。よさこい鳴子踊りの曲を必ず入れる。
③1チームあたりの踊子の数は150人まで。
④地方車の規定アリ。
まず、鳴子はこちらです⇒

運動会でYOSAKOIソーランなど、踊ったことがある人は一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
鳴らし方にコツがあり、手首のスナップが必要です。
また「地方車」は音楽を鳴らすトラックです。
このトラックに音楽機材や生のバンドが乗って演奏しながら進んでいきます。
迫力は何事にも代えがたいと私は思っています。
また装飾にもこだわっているチームも多く、賞も用意されています。
よさこいは踊っている側も見て応援している側もすごい熱量です。
また応援している側は踊り子をうちわで仰いだり、近所の方はドリンクを配ったりと「利他」の精神にもあふれています。
実際に自分が躍った際にも沿道の方からの応援に励まされ踊り切ることができました!
実際に踊っている様子⇒

今年のよさこいも大変感動しました。
地元が盛り上がっていくのはうれしく、その勢いに負けないよう自分も努力していこう!と感じました。
Q.不登校にならないためには?
居場所作り。つまり、信頼関係が大切だと思います。
信頼できる先生がいれば、生徒の登校しようというきっかけに繋がります。
私自身、中学生の時に足が学校へ向かない時期がありました。
その時に心配してくれる先生や同級生がいたことで、学校へ足が向くようになり、人前に出て発表することもできるようになってきました。
また、折れない心を作ることも重要です。
心が折れてしまうとそこまで頑張ってきたことが無になってしまうかもしれません。
学生の内に失敗は経験しておいた方が良いと思います。
そして失敗をバネにして次に進む経験も。
リタ学園を卒業してからもこの経験が活かせる生徒になれるよう、関わっていきたいと考えています!
2023.08.18
過去と「今日」と未来
はじめまして。リタ学園サポーター本部の樋口悠輝です。
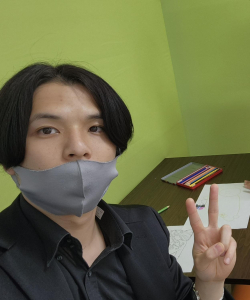
私はもともと香川県にあるRITA学園高等学校に大卒新卒で赴任し、そこで5年間教師をしておりました。
社会人6年目となる2023年4月に転職し、リタ学園サポーター本部のある兵庫県は神戸の地にやってきたわけであります。
神戸はあまりにも都会でまぶしく、日々緊張しながら通勤しています。
自分も早くシティーボーイの仲間入りをしたいものです。
今はリタ学園 神戸学習館のサポートをしながら、いわゆる学校事務や広報資料の作成、営業活動、様々な企画の計画を練る日々を過ごしております。
RITA学園で教師をしていた経験を活かしつつ、新しい刺激を感じることもでき、超エキサイティンな感じです。
心機一転、新生活が始まって数ヵ月経ちましたが、私には日々の暮らしを送る上で大切にしていることがあります。
“今日”を大切に過ごすことです。
22歳で教師という仕事に就き、担任としての生徒対応や教科担当としての教材作成、学校総務としてさまざまな行事の企画を行う毎日。
昨日の失敗を嘆き、明日がくることに怯えて日々を過ごすことが多かったのですが、「とりあえず先のことはあまり考えず、今日を大切にしよう」と思うようになり、多少前向きな気持ちになれたことをよく覚えています。
そこからの5年間でひとつわかったことがあります。
「今日」を大切に生きていけば、たとえどんな失敗があったとしても「過去は偉大な歴史になり、未来は大きな希望になっていく」ということです。
「小中学校、満足に登校できなかった。」
「高校を途中で辞めてしまった。」
「勉強についていけなくなってしまった。」
「将来の夢がない。」
「人とコミュニケーションをとることが苦手。」
「自分を大切にできない。」
大いに結構。
自分も含め、人にはいろいろな事情があり、時に不安定になることがあるのも当たり前のことです。
RITA学園高等学校、そしてリタ学園には、皆さんの過去を偉大な歴史に変え、不安だった未来を明るい希望に変えていく力があります。
そして、生徒ファーストで物事を考える魅力あふれる先生が、香川県、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、東京都、その他数多くの地域に大勢いらっしゃいます。
そんな先生方と協力しつつ、皆さんの輝く未来を作っていくお手伝いができれば幸いです。
Q.通信制高校の魅力とは?
多様な学び方を提供できるところ。
2023.05.19
データサイエンス
ビッグデータの有効活用が求められる時代に、ビッグデータを分析・解析して価値を生み出すためには、そこから課題を見つけ課題解決に向けた方法を探る力を身につけることです。
情報収集力や加工力、さらには表現力や発信力といった、いわゆるデータサイエンス力を備えることは今や不可欠となっています。
以前に勤務した学校の授業でデータサイエンスの手法を用いた活動を行うために、理科、数学、地歴・公民の先生たちが担当して、「住みたい街ランキング関西版2021-SUUMO」からランキングの根拠が何か?人々が住みたい街となるその要素とは何か?を探るという教科横断授業を行ったことがあります。
目的は生徒たちが今後の研究や探究活動をより充実したものにするためで、データサイエンスの手法について学ぶとともに、どのような街づくりが人々にとって、また自分たちにとって大切なのかを考えることでした。
データの収集は「政府統計の総合窓口(e-Stat)」を中心に、「統計データ分析コンペティション」や「地方公共団体データベースサイト」を活用して行いました。
日々の対応に追われてなかなか時間のない私たちが、利他の考え方に基づく不易な教育理念の上に立って、これからの通信制高等学校、サポートセンター、また技能連携施設が社会からのどのようなニーズに対応し、何を目指し、どのように発展していかなければならないかを考える一つの手段として、ビッグデータの分析や解析から社会全体を俯瞰する機会を設けてみるのも必要なことかもしれません。
Q.通信制高校の魅力とは?
以前、一般の通信制高校にあまり魅力を感じてなかった私が今感じていることは、本校のように一人ひとりの生徒と一生懸命関わろうとする教職員のいる通信制高校は唯一無二かもしれないということです。
魅力を生み出す通信制高校の出現を実感していることを魅力と感じています。
2023.04.09
「生きる」ということ
皆さんは映画を観ますか?
わたしは大学1回生の時に出会った方がきっかけで、年間100本の映画を鑑賞するというのがお決まりの目標になっています。
最近はマーベルシリーズを少しずつ見始めている途中ですが、今年感動した映画を一つ、ここで紹介したいと思います!
『かがみの孤城』
原作は、本屋大賞を受賞された辻村深月さんの小説で、他にも「ツナグ」(2011)や 「ドラえもん のび太の月面探査記」(2019)の脚本などを担当されています。
わたしは当初、『かがみの孤城』を劇場で鑑賞しようか迷っていたのですが、両親からの薦めもあり観に行きました。
この映画は、「学校に行きづらい」と感じている人や「悩み」を抱えている人にぜひ観てほしいです。
それぞれが学校に対して様々な不安を抱え、最初はバラバラだったキャラクターたちが、最終的には一致団結して立ち向かっていく。
わたしはそれぞれが悩みに立ち向かうシーンや、他のキャラクターとの掛け合いに、何度も涙があふれだしました。
そして、小さくても一歩踏み出してみよう。と勇気を貰えた作品でした。
「命」や「病気」について考えさせられるシーンもあり、映画を鑑賞して「生きる」ということの大切さを再認識できました。
Q.通信制高校の魅力とは?
「自由」なところだと思います。科目選択であったり、登校の自由さであったり。
通信制ではない高校よりは「自由」の幅が大きいです。
しかし、それには「責任」も伴います。
そのため、時には自分の選択に自信がなくなることもあると思います。
そんなときは一人で抱え込まず、先生を存分に頼ってください。いつでもウェルカムです!


